上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書くことで広告が消せます。
2014年01月01日

謹賀新年
昨年も僕の拙いブログをお読みいただき
ありがとうございました
今年も変わらぬお付き合いのほど
よろしくお願いいたします
平成26年元旦
昨年も僕の拙いブログをお読みいただき
ありがとうございました
今年も変わらぬお付き合いのほど
よろしくお願いいたします
平成26年元旦
2013年05月01日
【休日・祭日は休刊日】
 いつもお読みいただいている読者の方、ありがとうございます。
いつもお読みいただいている読者の方、ありがとうございます。
勝手な都合で恐縮なのですが、休日・祭日は休刊日にさせていただいてじっくりと週日にいい記事を載せたいと思います。
写真は立花山の樹齢300年にもなるクスノキの原生林です。しばし、心が洗われるような森林浴に浸れる空間です。
みなさんも一度行ってみませんか?
《参考》・・・あと数枚、クスノキの写真を旅行記にアップしています。
・「近場の穴場-都市近郊にある原生林」(luckymentaiさんの旅行ブログ)
 いつもお読みいただいている読者の方、ありがとうございます。
いつもお読みいただいている読者の方、ありがとうございます。勝手な都合で恐縮なのですが、休日・祭日は休刊日にさせていただいてじっくりと週日にいい記事を載せたいと思います。
写真は立花山の樹齢300年にもなるクスノキの原生林です。しばし、心が洗われるような森林浴に浸れる空間です。
みなさんも一度行ってみませんか?
《参考》・・・あと数枚、クスノキの写真を旅行記にアップしています。
・「近場の穴場-都市近郊にある原生林」(luckymentaiさんの旅行ブログ)
2013年01月01日
 昨年も僕の拙いブログをお読みいただき
昨年も僕の拙いブログをお読みいただきありがとうございました
今年も変わらぬお付き合いのほど
よろしくお願いいたします
平成25年元旦
2012年12月31日
【今年の10大ニュース】
いよいよ今年も今日で終わり。年の最後に2012年を振り返るべく、読売新聞の読者が選んだ10大ニュースを見てみましょう。先ずは「日本編」。
1.ノーベル生理学・医学賞に山中教授
2.東京スカイツリー開業
3.ロンドン五輪、史上最多のメダル38個
4.政権問う師走の衆院総選挙
5.尖閣国有化で日中関係悪化
6.金環日食、932年ぶり広範囲観測
7.中央道トンネルで崩落、9人死亡
8.巨人が3年ぶり22度目の日本一
9.地下鉄サリン事件で特別手配の菊地容疑者ら逮捕、オウム捜査終結へ
10.兵庫県尼崎市のドラム缶遺体事件、連続遺体遺棄・行方不明事件に発展
昨年あまりにも大きな災害である東日本大震災そして福島第一原子力発電所事故を経験した翌年となった2012年、明るいニュースを求める気持ちと実際の明るい出来事が上位3位までの山中教授のノーベル賞、東京スカイツリー開業、ロンドンオリンピックのメダル獲得という投票結果に表れてきたのでしょうか。また、不安や不安定な世情が少しでも安定を求めるあまり、衆院選での自民党大勝をもたらしたのかもしれません。巨人の日本一が8位に入っているところが読売のランキングらしいですね。
【国際編10大ニュース】
では同じく読売新聞から国際編の10大ニュースをどうぞ。
1.米大統領選でオバマ氏が再選
2.中国共産党総書記に習近平氏
3.金正恩氏が朝鮮労働党第1書記に
4.英エリザベス女王の即位60年で祝賀行事
5.ミャンマー議会補選でスー・チー氏当選
6.露大統領にプーチン首相が当選
7.大型ハリケーン「サンディ」、米で死者100人以上
8.シリア内戦が泥沼化
9.NASA無人探査車が火星に着陸
10.スペインがユーロ圏に金融支援要請、欧州の財政・金融危機続く
今年の海外の10大ニュースの上位には、アメリカ、中国、北朝鮮のトップ交代が入りました。その他にもミャンマーのスー・チー氏やロシアのプーチン首相が入っていて、2012年はまさに世界も政治の年だったことがわかります。2013年は新しいリーダーのもとで新しい世界秩序の再構築に向けて様々な動きが表面化してくるでしょう。
【僕のブログの10大ニュース】
そして最後に独断と偏見で選んだ僕のブログの10大ニュースを発表します。
1.「ゼロからの出直し-全原発停止」・・・・・・・・5月7日記事
2.「絶望からの出発-自民圧勝の後に来るもの」・・12月17日記事
3.「アラブから日本へ-首相官邸前再稼働反対デモの重み」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月25日記事
4.「米国が世界最大の産油国に」・・・・・・・・・11月13日記事
5.「過半の国民は原発に依存しない社会を望む」・・8月29日記事
6.「首相と反原発団体が面談 」・・・・・・・・・・8月23日記事
7.「豊田会長の「勇気」-美しき故郷発言」・・・・9月24日記事
8.「韓国のダイナミズム-女性大統領の誕生」・・・12月20日記事
9.「国会事故調の報告を蹂躙した大飯再稼働」・・・・7月6日記事
10.「党派を超えて脱原発を目指せ!」・・・・・・・11月26日記事
今年は僕にとっての最大のニュースは、何といっても5月5日に日本の54基の全原発が停止したことです。その後大飯原発の再稼働によって原発ゼロはほんの2カ月足らずで終わったのですが、それでも原発推進一辺倒だった国の原子力政策が岐路に立ったことは間違いありません。そして2番目のニュースは12月16日の衆院選挙による自民党の圧勝、それに続く安倍政権の誕生です。安倍政権は発足後矢継ぎ早に原発新設、再稼働、核燃料サイクルの継続を表明し、原子力問題の先送りを国民の脱原発の思いを完全に無視して強行することを「約束」しました。これほどの暴挙を許しているのは衆院選の自民党圧勝という結果を原発にまで国民が自民党政権に白紙委任状をくれたと勝手に解釈している彼らの独善です。このままではそう簡単に逆戻りするとは思いませんが、それでも3/11前の原子力推進体制に戻りつつあることは間違いありません。大量の放射能汚染によって今でも福島とその周辺の方々の苦難は続いています。安倍首相は福島入りして原発新設をほのめかしたそうですが、そんなことよりも福島の被災者を救うほうが先です。2013年は少しでもこの流れを止められることを期待するばかりです。
その意味で、今年のニュースの中でも官邸前デモの広がりや脱原発を求める大きな国民世論の動きなど勇気づけられる記事も取り上げました。
《参考》
・「今年の締めくくり10大ニュース」・・・・2011年12月31日の僕のブログ記事
いよいよ今年も今日で終わり。年の最後に2012年を振り返るべく、読売新聞の読者が選んだ10大ニュースを見てみましょう。先ずは「日本編」。
1.ノーベル生理学・医学賞に山中教授
2.東京スカイツリー開業
3.ロンドン五輪、史上最多のメダル38個
4.政権問う師走の衆院総選挙
5.尖閣国有化で日中関係悪化
6.金環日食、932年ぶり広範囲観測
7.中央道トンネルで崩落、9人死亡
8.巨人が3年ぶり22度目の日本一
9.地下鉄サリン事件で特別手配の菊地容疑者ら逮捕、オウム捜査終結へ
10.兵庫県尼崎市のドラム缶遺体事件、連続遺体遺棄・行方不明事件に発展
昨年あまりにも大きな災害である東日本大震災そして福島第一原子力発電所事故を経験した翌年となった2012年、明るいニュースを求める気持ちと実際の明るい出来事が上位3位までの山中教授のノーベル賞、東京スカイツリー開業、ロンドンオリンピックのメダル獲得という投票結果に表れてきたのでしょうか。また、不安や不安定な世情が少しでも安定を求めるあまり、衆院選での自民党大勝をもたらしたのかもしれません。巨人の日本一が8位に入っているところが読売のランキングらしいですね。
【国際編10大ニュース】
では同じく読売新聞から国際編の10大ニュースをどうぞ。
1.米大統領選でオバマ氏が再選
2.中国共産党総書記に習近平氏
3.金正恩氏が朝鮮労働党第1書記に
4.英エリザベス女王の即位60年で祝賀行事
5.ミャンマー議会補選でスー・チー氏当選
6.露大統領にプーチン首相が当選
7.大型ハリケーン「サンディ」、米で死者100人以上
8.シリア内戦が泥沼化
9.NASA無人探査車が火星に着陸
10.スペインがユーロ圏に金融支援要請、欧州の財政・金融危機続く
今年の海外の10大ニュースの上位には、アメリカ、中国、北朝鮮のトップ交代が入りました。その他にもミャンマーのスー・チー氏やロシアのプーチン首相が入っていて、2012年はまさに世界も政治の年だったことがわかります。2013年は新しいリーダーのもとで新しい世界秩序の再構築に向けて様々な動きが表面化してくるでしょう。
【僕のブログの10大ニュース】
そして最後に独断と偏見で選んだ僕のブログの10大ニュースを発表します。
1.「ゼロからの出直し-全原発停止」・・・・・・・・5月7日記事
2.「絶望からの出発-自民圧勝の後に来るもの」・・12月17日記事
3.「アラブから日本へ-首相官邸前再稼働反対デモの重み」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月25日記事
4.「米国が世界最大の産油国に」・・・・・・・・・11月13日記事
5.「過半の国民は原発に依存しない社会を望む」・・8月29日記事
6.「首相と反原発団体が面談 」・・・・・・・・・・8月23日記事
7.「豊田会長の「勇気」-美しき故郷発言」・・・・9月24日記事
8.「韓国のダイナミズム-女性大統領の誕生」・・・12月20日記事
9.「国会事故調の報告を蹂躙した大飯再稼働」・・・・7月6日記事
10.「党派を超えて脱原発を目指せ!」・・・・・・・11月26日記事
今年は僕にとっての最大のニュースは、何といっても5月5日に日本の54基の全原発が停止したことです。その後大飯原発の再稼働によって原発ゼロはほんの2カ月足らずで終わったのですが、それでも原発推進一辺倒だった国の原子力政策が岐路に立ったことは間違いありません。そして2番目のニュースは12月16日の衆院選挙による自民党の圧勝、それに続く安倍政権の誕生です。安倍政権は発足後矢継ぎ早に原発新設、再稼働、核燃料サイクルの継続を表明し、原子力問題の先送りを国民の脱原発の思いを完全に無視して強行することを「約束」しました。これほどの暴挙を許しているのは衆院選の自民党圧勝という結果を原発にまで国民が自民党政権に白紙委任状をくれたと勝手に解釈している彼らの独善です。このままではそう簡単に逆戻りするとは思いませんが、それでも3/11前の原子力推進体制に戻りつつあることは間違いありません。大量の放射能汚染によって今でも福島とその周辺の方々の苦難は続いています。安倍首相は福島入りして原発新設をほのめかしたそうですが、そんなことよりも福島の被災者を救うほうが先です。2013年は少しでもこの流れを止められることを期待するばかりです。
その意味で、今年のニュースの中でも官邸前デモの広がりや脱原発を求める大きな国民世論の動きなど勇気づけられる記事も取り上げました。
《参考》
・「今年の締めくくり10大ニュース」・・・・2011年12月31日の僕のブログ記事
タグ :10大ニュース
2012年10月15日
【待望の釣果】
 やっと、やっと、1年ぶりにヒラメをゲットすることができました。
やっと、やっと、1年ぶりにヒラメをゲットすることができました。
釣れたのは福岡県新宮町の相島浮波止。昨日の日曜日、念願のヒラメは午前10時ごろに僕の釣竿に食いついてくれました。ありがとう、ヒラメくん。
思えば、ヒラメを釣り上げたのは、昨年の10月10日でした。あれからほぼ1年。長い道のりでした。といっても、今年はまだ2回目の釣行です。ここ1年ほど仕事で週末もイベントごとに出ることが多く、なかなか釣りに行けない日が多かったのですが、これで一息です。
【二人で釣行】
 今回も、釣り友と二人での釣行でした。午前5時50分、いつものように福岡県の新宮港を遊漁船で出航。気温は15度前後と例年通りでしたが、それでも朝は冷えます。新宮港にも朝4時頃から波止に大勢の釣り人が来てすでに釣りをしていましたが、渡船場にも数隻の遊漁船がすでに来ていて青物狙いの釣り客が大勢集まっていました。僕らの乗る「福昇丸」にも15人の釣り客が乗り込み、船は相島へ向かいました。
今回も、釣り友と二人での釣行でした。午前5時50分、いつものように福岡県の新宮港を遊漁船で出航。気温は15度前後と例年通りでしたが、それでも朝は冷えます。新宮港にも朝4時頃から波止に大勢の釣り人が来てすでに釣りをしていましたが、渡船場にも数隻の遊漁船がすでに来ていて青物狙いの釣り客が大勢集まっていました。僕らの乗る「福昇丸」にも15人の釣り客が乗り込み、船は相島へ向かいました。
 6時過ぎには浮波止に上がり、友人は浮波止で釣り開始、僕は相島漁港に行って他の釣り客2人でさっそく餌となる小アジ釣りを開始。なんとか小アジを20尾ほど確保、浮波止に戻って次々とヒラメの仕掛け竿を準備しました。
6時過ぎには浮波止に上がり、友人は浮波止で釣り開始、僕は相島漁港に行って他の釣り客2人でさっそく餌となる小アジ釣りを開始。なんとか小アジを20尾ほど確保、浮波止に戻って次々とヒラメの仕掛け竿を準備しました。
最初のヒットは、友人の竿に来ました。しかし上げてみるとエソ。そのあとは友人にアオリイカが来た以外はほとんど当たりなし。
満潮時刻の8時40分を過ぎること1時間半、浮波止と浮波止の間に置いていた置き竿がヒット。待望のヒラメをゲットしました。45センチの中型サイズ。やった!!!
釣り友は今回は駄目でしたが、これは順番。きっと次回は大物をゲットするよう祈ってます。
【夕餉の支度に奔走】
 さて、1時の船で新宮港に戻り、2時に家についてからが大変でした。直ぐに近くの魚屋さんでさばいてもらい、釣り道具を片付けて夕食の支度です。といっても料理はワイフが手際よくやってくれました。
さて、1時の船で新宮港に戻り、2時に家についてからが大変でした。直ぐに近くの魚屋さんでさばいてもらい、釣り道具を片付けて夕食の支度です。といっても料理はワイフが手際よくやってくれました。
そして、母を呼んでヒラメの刺身と、それから一緒に釣ったカワハギの味噌汁、子鯛の煮つけ、小アジの唐揚で勝利の美酒を堪能しました。
 やっと、やっと、1年ぶりにヒラメをゲットすることができました。
やっと、やっと、1年ぶりにヒラメをゲットすることができました。 釣れたのは福岡県新宮町の相島浮波止。昨日の日曜日、念願のヒラメは午前10時ごろに僕の釣竿に食いついてくれました。ありがとう、ヒラメくん。
思えば、ヒラメを釣り上げたのは、昨年の10月10日でした。あれからほぼ1年。長い道のりでした。といっても、今年はまだ2回目の釣行です。ここ1年ほど仕事で週末もイベントごとに出ることが多く、なかなか釣りに行けない日が多かったのですが、これで一息です。
【二人で釣行】
 今回も、釣り友と二人での釣行でした。午前5時50分、いつものように福岡県の新宮港を遊漁船で出航。気温は15度前後と例年通りでしたが、それでも朝は冷えます。新宮港にも朝4時頃から波止に大勢の釣り人が来てすでに釣りをしていましたが、渡船場にも数隻の遊漁船がすでに来ていて青物狙いの釣り客が大勢集まっていました。僕らの乗る「福昇丸」にも15人の釣り客が乗り込み、船は相島へ向かいました。
今回も、釣り友と二人での釣行でした。午前5時50分、いつものように福岡県の新宮港を遊漁船で出航。気温は15度前後と例年通りでしたが、それでも朝は冷えます。新宮港にも朝4時頃から波止に大勢の釣り人が来てすでに釣りをしていましたが、渡船場にも数隻の遊漁船がすでに来ていて青物狙いの釣り客が大勢集まっていました。僕らの乗る「福昇丸」にも15人の釣り客が乗り込み、船は相島へ向かいました。  6時過ぎには浮波止に上がり、友人は浮波止で釣り開始、僕は相島漁港に行って他の釣り客2人でさっそく餌となる小アジ釣りを開始。なんとか小アジを20尾ほど確保、浮波止に戻って次々とヒラメの仕掛け竿を準備しました。
6時過ぎには浮波止に上がり、友人は浮波止で釣り開始、僕は相島漁港に行って他の釣り客2人でさっそく餌となる小アジ釣りを開始。なんとか小アジを20尾ほど確保、浮波止に戻って次々とヒラメの仕掛け竿を準備しました。 最初のヒットは、友人の竿に来ました。しかし上げてみるとエソ。そのあとは友人にアオリイカが来た以外はほとんど当たりなし。
満潮時刻の8時40分を過ぎること1時間半、浮波止と浮波止の間に置いていた置き竿がヒット。待望のヒラメをゲットしました。45センチの中型サイズ。やった!!!
釣り友は今回は駄目でしたが、これは順番。きっと次回は大物をゲットするよう祈ってます。
【夕餉の支度に奔走】
 さて、1時の船で新宮港に戻り、2時に家についてからが大変でした。直ぐに近くの魚屋さんでさばいてもらい、釣り道具を片付けて夕食の支度です。といっても料理はワイフが手際よくやってくれました。
さて、1時の船で新宮港に戻り、2時に家についてからが大変でした。直ぐに近くの魚屋さんでさばいてもらい、釣り道具を片付けて夕食の支度です。といっても料理はワイフが手際よくやってくれました。 そして、母を呼んでヒラメの刺身と、それから一緒に釣ったカワハギの味噌汁、子鯛の煮つけ、小アジの唐揚で勝利の美酒を堪能しました。
2012年07月05日
【ブログ生活7年】
皆さん、このニュースブログ「博多っ子の元気通信」に今日もお付き合いいただきありがとうございます。
 僕がブログを書き始めたのは、2005年3月6日。実に7年3ヶ月近く書いていることになります。自分でもここまで続けることになるとは思いませんでした。
僕がブログを書き始めたのは、2005年3月6日。実に7年3ヶ月近く書いていることになります。自分でもここまで続けることになるとは思いませんでした。
一体何が楽しくてやっているのか、馬鹿じゃないかと思われている向きもあろうかと思い、少し僕のブログ生活についてお話します。
最初のきっかけは、中国のコンサルタントをしている友人がブログを開設していることを知って、自分もやってみようと思ったことでした。その友人も食べ歩き日記で一時勇名をはせたブロガーに勧められて始めたとのことでしたが、インターネットには当時あまり関心がなさそうだった僕の友人がブログをしていることに多少なりともショックを受けたことを今でも覚えています。その頃、すでに世の中ではブログが相当流行っていました。
最初のブログ記事は、3月6日のブログ「雪の日曜日に企業買収を考える」でした。
サラリーマンの独り言を「つれづれ日記」という形で書いてみようと思ったのですが、その後ブログのタイトルも「博多っ子の元気通信」と一新して、書いているうちにその面白さについついはまり込んでしまったというわけです。それにしてもこんなに長く続けることになろうとは思いませんでした。当初は不定期で書いていたのですが、その後友人の勧めで毎日書くようになり、最近は週末と祝祭日以外の日に書いています。
長い間、タイム誌の記事を中心に日々のニュースを織り交ぜながら書いてきましたが、昨年の3月11日の福島第一原発の事故をきっかけに全面的に方針転換をし、今に至っています。それは1986年4月に起こったチェルノブイリ原発事故をきっかけに日本の原子力政策や原発に対して不信感を持ち続けていたことと日本での原発事故の再発を危惧してきたことがまさに現実となり、もう黙ってはいられない、誰かにこの思いを伝えたいと思ったからです。
【ブログの効用】
原発問題を集中的に取り上げている現在の動機は別にして、僕にとってそもそもこれまでブログを書くことで得てきたものは何かについて少しお話します。
先ずはなんといっても個性豊かなブロガー仲間が出来たことです。インターネットがなかった時代には考えられなかった「時空を超えた」仲間達。これが最大の収穫でした。そしてmixiでその輪がまた広がりました。ただ、始めた当時から今まで継続している人はそう多くありません。でも友情は続いてます。さらにここ数年は、ソーシャルネットワークの主体がmixiからfacebookへと変わり、実名でのやりとりとなって、ブログとも連動するようにしてからはその広がりはさらに大きくなりました。つい昨晩もfacebookでいつもやりとりしている友人の勧めで原発問題の重要性を語る機会を作ってもらい、初対面も含めた6人ほどの小じんまりした集まりでワイワイ議論しあい、とても貴重な時間を過ごしました。
次に、日々のニュースに対してコメントをすることで、世の中の動きをただ眺めているだけでなく、「これは何故だ」とか「こういう事実に対して自分はどう考えるべきか」といった視点を常に持つようになったことです。この効果は実に大きい。「序・破・急」のロジックを意識して、できるだけ三段に分けて書いているのですが、自分の考えを常にまとめるという癖がつき、仕事をする上でも役に立っています。
【物を書く楽しさと主張することの大切さ】
そして最後は、物を書く楽しさ、そして主張することの大切さをブログから得ていることです。
人は誰でも自分のことを知ってもらいたい、世の中のことをもっと知りたい、それらを文字として書いて見たいという欲求があるみたいです。その欲求に楽しさが加わったとき、それがブログという形に結晶していくのだと思います。
特に毎日の世の中の出来事から面白いと思う話題をピックアップして自分の言葉で伝えるというのは、結構ワクワクするものです。
さらにすでにお伝えした通り、ここ1年半ほどはタイム誌の記事や様々なジャンルの新聞記事をテーマに書くことを一旦休止して、原発問題に的を絞って事の重大性を訴え続けています。ブログはfacebookと連動させていますので、原発問題に関する主張は匿名の主張ではなくなり、いいかげんなことは言えなくなった半面、実名で真剣な訴えを聞いてもらえる場となっています。
ブログを見ていただいているみなさん、どうぞこれからも末長くお付き合いいただければ幸いです。
皆さん、このニュースブログ「博多っ子の元気通信」に今日もお付き合いいただきありがとうございます。
 僕がブログを書き始めたのは、2005年3月6日。実に7年3ヶ月近く書いていることになります。自分でもここまで続けることになるとは思いませんでした。
僕がブログを書き始めたのは、2005年3月6日。実に7年3ヶ月近く書いていることになります。自分でもここまで続けることになるとは思いませんでした。一体何が楽しくてやっているのか、馬鹿じゃないかと思われている向きもあろうかと思い、少し僕のブログ生活についてお話します。
最初のきっかけは、中国のコンサルタントをしている友人がブログを開設していることを知って、自分もやってみようと思ったことでした。その友人も食べ歩き日記で一時勇名をはせたブロガーに勧められて始めたとのことでしたが、インターネットには当時あまり関心がなさそうだった僕の友人がブログをしていることに多少なりともショックを受けたことを今でも覚えています。その頃、すでに世の中ではブログが相当流行っていました。
最初のブログ記事は、3月6日のブログ「雪の日曜日に企業買収を考える」でした。
サラリーマンの独り言を「つれづれ日記」という形で書いてみようと思ったのですが、その後ブログのタイトルも「博多っ子の元気通信」と一新して、書いているうちにその面白さについついはまり込んでしまったというわけです。それにしてもこんなに長く続けることになろうとは思いませんでした。当初は不定期で書いていたのですが、その後友人の勧めで毎日書くようになり、最近は週末と祝祭日以外の日に書いています。
長い間、タイム誌の記事を中心に日々のニュースを織り交ぜながら書いてきましたが、昨年の3月11日の福島第一原発の事故をきっかけに全面的に方針転換をし、今に至っています。それは1986年4月に起こったチェルノブイリ原発事故をきっかけに日本の原子力政策や原発に対して不信感を持ち続けていたことと日本での原発事故の再発を危惧してきたことがまさに現実となり、もう黙ってはいられない、誰かにこの思いを伝えたいと思ったからです。
【ブログの効用】
原発問題を集中的に取り上げている現在の動機は別にして、僕にとってそもそもこれまでブログを書くことで得てきたものは何かについて少しお話します。
先ずはなんといっても個性豊かなブロガー仲間が出来たことです。インターネットがなかった時代には考えられなかった「時空を超えた」仲間達。これが最大の収穫でした。そしてmixiでその輪がまた広がりました。ただ、始めた当時から今まで継続している人はそう多くありません。でも友情は続いてます。さらにここ数年は、ソーシャルネットワークの主体がmixiからfacebookへと変わり、実名でのやりとりとなって、ブログとも連動するようにしてからはその広がりはさらに大きくなりました。つい昨晩もfacebookでいつもやりとりしている友人の勧めで原発問題の重要性を語る機会を作ってもらい、初対面も含めた6人ほどの小じんまりした集まりでワイワイ議論しあい、とても貴重な時間を過ごしました。
次に、日々のニュースに対してコメントをすることで、世の中の動きをただ眺めているだけでなく、「これは何故だ」とか「こういう事実に対して自分はどう考えるべきか」といった視点を常に持つようになったことです。この効果は実に大きい。「序・破・急」のロジックを意識して、できるだけ三段に分けて書いているのですが、自分の考えを常にまとめるという癖がつき、仕事をする上でも役に立っています。
【物を書く楽しさと主張することの大切さ】
そして最後は、物を書く楽しさ、そして主張することの大切さをブログから得ていることです。
人は誰でも自分のことを知ってもらいたい、世の中のことをもっと知りたい、それらを文字として書いて見たいという欲求があるみたいです。その欲求に楽しさが加わったとき、それがブログという形に結晶していくのだと思います。
特に毎日の世の中の出来事から面白いと思う話題をピックアップして自分の言葉で伝えるというのは、結構ワクワクするものです。
さらにすでにお伝えした通り、ここ1年半ほどはタイム誌の記事や様々なジャンルの新聞記事をテーマに書くことを一旦休止して、原発問題に的を絞って事の重大性を訴え続けています。ブログはfacebookと連動させていますので、原発問題に関する主張は匿名の主張ではなくなり、いいかげんなことは言えなくなった半面、実名で真剣な訴えを聞いてもらえる場となっています。
ブログを見ていただいているみなさん、どうぞこれからも末長くお付き合いいただければ幸いです。
2012年04月27日
【動物も左利き?】
動物たちもみんな左利きがあるんですね。
 『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。
『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。
同紙によると、研究者たちはこれまで、左利き、右利きがあるのはヒトに限定されていると考えていたが、最近ではほとんどすべての生物が左右どちらかを主に使うよう進化したことが分かったという。
魚の場合、自分の敵となる魚や動物が接近してきた場合、右利きの目をもつ魚は時計と同じ右回りに逃げ、左利きの魚は左回りに逃げる。左右差があった方が素早く反応でき、生存の確率が高まる。
また、英クイーンズ大学(北アイルランド・ベルファスト)の研究によれば、性別で違いもあることも分かった。猫の場合、雌猫は瓶などから食べ物を引き出そうとする際、右手(右前脚)を使う傾向があるのに、雄猫は左手を使おうとする。犬の場合も同様に当てはまるという。』(5月2日付ロイター通信)
【仲間が増えた】
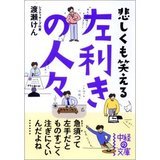 それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。
それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。
それが数十年前から、「私の彼は左利き」とかいう歌が流行ったり、外国の元首や有名人が左手でサインしていたりと、日本社会の常識が世界の常識ではないことが少しずつ浸透してきて今ではあまり左利きに対する差別はさほど強くはなくなりました。(ちなみにオバマ大統領も左手でサインしています)
そんなところに今回は動物社会でも左利きが存在し、しかもそれが生存競争にも有利に働いているというのですから、左利きの僕なんかにしてみれば嬉しい限りです。これからは異能の人が活躍する時代です。右脳人間には左利きか多いとも言います。左利きのみなさん、これからも右利き社会をどんどん変革していきましょう!!!!
動物たちもみんな左利きがあるんですね。
 『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。
『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。同紙によると、研究者たちはこれまで、左利き、右利きがあるのはヒトに限定されていると考えていたが、最近ではほとんどすべての生物が左右どちらかを主に使うよう進化したことが分かったという。
魚の場合、自分の敵となる魚や動物が接近してきた場合、右利きの目をもつ魚は時計と同じ右回りに逃げ、左利きの魚は左回りに逃げる。左右差があった方が素早く反応でき、生存の確率が高まる。
また、英クイーンズ大学(北アイルランド・ベルファスト)の研究によれば、性別で違いもあることも分かった。猫の場合、雌猫は瓶などから食べ物を引き出そうとする際、右手(右前脚)を使う傾向があるのに、雄猫は左手を使おうとする。犬の場合も同様に当てはまるという。』(5月2日付ロイター通信)
【仲間が増えた】
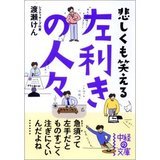 それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。
それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。それが数十年前から、「私の彼は左利き」とかいう歌が流行ったり、外国の元首や有名人が左手でサインしていたりと、日本社会の常識が世界の常識ではないことが少しずつ浸透してきて今ではあまり左利きに対する差別はさほど強くはなくなりました。(ちなみにオバマ大統領も左手でサインしています)
そんなところに今回は動物社会でも左利きが存在し、しかもそれが生存競争にも有利に働いているというのですから、左利きの僕なんかにしてみれば嬉しい限りです。これからは異能の人が活躍する時代です。右脳人間には左利きか多いとも言います。左利きのみなさん、これからも右利き社会をどんどん変革していきましょう!!!!
2011年12月31日
【今年の10大ニュース】
いよいよ今年も今日で終わり。年の最後に2012年を振り返るべく、読売新聞の読者が選んだ10大ニュースを見てみましょう。先ずは「日本編」。
1.東日本大震災、死者・不明者約2万人
2.サッカー「なでしこジャパン」世界一
3.福島第一原発事故で深刻な被害
4.大相撲で八百長発覚、春場所中止に
5.新首相に野田佳彦氏
6.スカイツリー「世界一」634メートルに到達
7.大型台風上陸相次ぎ記録的被害
8.大阪ダブル選、「都構想」で共闘の橋下氏が大阪市長、松井氏が府知事に初当選
9.テレビ放送が地デジに移行
10.節電の夏、37年ぶり電力使用制限令
今年のニッポンは、とてつもない災害に見舞われた年となりました。3月11日に起こった東日本大震災、巨大津波、そして福島第一原発事故。この日を境にして、ニッポンという国の形が実際に地図の上でも動いただけでなく、あらゆる意味で「この国のカタチ」が変わった、そして変わらなければならなくなりました。この大災害に比べれば他のどのニュースもあまりにも小さく見えるのは僕だけでしょうか。
【国際編10大ニュース】
では同じく読売新聞から国際編の10大ニュースをどうぞ。
1.タイで洪水被害、日系企業も大打撃
2.ウサマ・ビンラーディン殺害
3.チュニジアで長期独裁政権が崩壊、エジプト、リビアにも「アラブの春」
4.ニュージーランド地震で日本人28人を含む180人以上死亡
5.ユーロ危機深刻化、欧州各国に波及
6.中国高速鉄道で追突事故、40人死亡
7.米アップル社のスティーブ・ジョブズ会長が死去
8.世界人口が70億人突破
9.中国が日本を抜き世界第2の経済大国に
10.英ウィリアム王子が結婚
今年の海外の10大ニュースの上位にも、タイの大洪水やニュージーランドの大地震が入りました。大規模な自然災害が世界でも頻発し、地球全体でも気候変動や地殻変動が人々の暮らしを脅かしていることがわかります。そして自然の変化は人間の在り方にも大きな影響を及ぼしますが、その典型的な動きがチュニジアに端を発した中東の民主化のうねりだったのではないでしょうか。世界が音を立てて変わりつつあるという予感がした1年でした。
【僕のブログの10大ニュース】
そして最後に独断と偏見で選んだ僕のブログの10大ニュースを発表します。
1.「メルトダウンの恐怖-福島第一原発」・・・3月13日記事
2.「破局回避を天に祈る―福島第一原発」・・・・3月15日記事
3.「運転員不在―福島第一原発」・・・・・・・3月16日記事
4.「福島第一原発の惨禍に想う」・・・・・・・・・3月17日記事
5.「原発事故に想う―福島第一原発」・・・・・・・3月19日記事
6.「空気から食品へ―放射能の脅威 」・・・・・・3月20日記事
7.「原発事故に想う―福島第一原発その2」・・・・3月21日記事
8.「安堵と不安の連鎖続く―福島第一原発 」・・・・3月22日記事
9.「急速に進む「恐れていた事態」―食品・水・土壌の放射能」・・3月24日記事
10.「原発事故後に見えてきたもの―福島第一原発」・・3月27日記事
今年は僕にとっての最大のニュースは、何といっても福島第一原発の核惨事です。したがって異例ですが、10大ニュースすべてを原発事故が起こって数週間の記事だけにしました。1986年4月26日のチェルノブイリ原発の事故以来、日本で起こってほしくないと思っていたことが現実に福島で起こった。これは本当に恐怖でした。3月11日の事故発生以来の数日間は夜も眠れないくらいの恐怖を味わいました。もしかしたらあの数日間で日本が壊滅していたかもしれないと思うと今でもその当時書いた記事を読みなおすとその当時の恐怖がよみがえります。今も数十万人の方々が家も土地も職も家族も失い、故郷を失ったまま漂流を余儀なくされていると思うと胸が痛みます。これほどの大事故を起こした政府、東電、そして原子力ムラの住民と言われる関係者は厳罰に処せられるべきだと思いますし、これから重い十字架を背負って被災された方々の償いを一生にわたってしてもらいたいと思います。年が明けてもこの事故については追及し、監視し続けたいと思っています。
《参考》
・「今年の締めくくり10大ニュース」・・・・2010年12月31日の僕のブログ記事
いよいよ今年も今日で終わり。年の最後に2012年を振り返るべく、読売新聞の読者が選んだ10大ニュースを見てみましょう。先ずは「日本編」。
1.東日本大震災、死者・不明者約2万人
2.サッカー「なでしこジャパン」世界一
3.福島第一原発事故で深刻な被害
4.大相撲で八百長発覚、春場所中止に
5.新首相に野田佳彦氏
6.スカイツリー「世界一」634メートルに到達
7.大型台風上陸相次ぎ記録的被害
8.大阪ダブル選、「都構想」で共闘の橋下氏が大阪市長、松井氏が府知事に初当選
9.テレビ放送が地デジに移行
10.節電の夏、37年ぶり電力使用制限令
今年のニッポンは、とてつもない災害に見舞われた年となりました。3月11日に起こった東日本大震災、巨大津波、そして福島第一原発事故。この日を境にして、ニッポンという国の形が実際に地図の上でも動いただけでなく、あらゆる意味で「この国のカタチ」が変わった、そして変わらなければならなくなりました。この大災害に比べれば他のどのニュースもあまりにも小さく見えるのは僕だけでしょうか。
【国際編10大ニュース】
では同じく読売新聞から国際編の10大ニュースをどうぞ。
1.タイで洪水被害、日系企業も大打撃
2.ウサマ・ビンラーディン殺害
3.チュニジアで長期独裁政権が崩壊、エジプト、リビアにも「アラブの春」
4.ニュージーランド地震で日本人28人を含む180人以上死亡
5.ユーロ危機深刻化、欧州各国に波及
6.中国高速鉄道で追突事故、40人死亡
7.米アップル社のスティーブ・ジョブズ会長が死去
8.世界人口が70億人突破
9.中国が日本を抜き世界第2の経済大国に
10.英ウィリアム王子が結婚
今年の海外の10大ニュースの上位にも、タイの大洪水やニュージーランドの大地震が入りました。大規模な自然災害が世界でも頻発し、地球全体でも気候変動や地殻変動が人々の暮らしを脅かしていることがわかります。そして自然の変化は人間の在り方にも大きな影響を及ぼしますが、その典型的な動きがチュニジアに端を発した中東の民主化のうねりだったのではないでしょうか。世界が音を立てて変わりつつあるという予感がした1年でした。
【僕のブログの10大ニュース】
そして最後に独断と偏見で選んだ僕のブログの10大ニュースを発表します。
1.「メルトダウンの恐怖-福島第一原発」・・・3月13日記事
2.「破局回避を天に祈る―福島第一原発」・・・・3月15日記事
3.「運転員不在―福島第一原発」・・・・・・・3月16日記事
4.「福島第一原発の惨禍に想う」・・・・・・・・・3月17日記事
5.「原発事故に想う―福島第一原発」・・・・・・・3月19日記事
6.「空気から食品へ―放射能の脅威 」・・・・・・3月20日記事
7.「原発事故に想う―福島第一原発その2」・・・・3月21日記事
8.「安堵と不安の連鎖続く―福島第一原発 」・・・・3月22日記事
9.「急速に進む「恐れていた事態」―食品・水・土壌の放射能」・・3月24日記事
10.「原発事故後に見えてきたもの―福島第一原発」・・3月27日記事
今年は僕にとっての最大のニュースは、何といっても福島第一原発の核惨事です。したがって異例ですが、10大ニュースすべてを原発事故が起こって数週間の記事だけにしました。1986年4月26日のチェルノブイリ原発の事故以来、日本で起こってほしくないと思っていたことが現実に福島で起こった。これは本当に恐怖でした。3月11日の事故発生以来の数日間は夜も眠れないくらいの恐怖を味わいました。もしかしたらあの数日間で日本が壊滅していたかもしれないと思うと今でもその当時書いた記事を読みなおすとその当時の恐怖がよみがえります。今も数十万人の方々が家も土地も職も家族も失い、故郷を失ったまま漂流を余儀なくされていると思うと胸が痛みます。これほどの大事故を起こした政府、東電、そして原子力ムラの住民と言われる関係者は厳罰に処せられるべきだと思いますし、これから重い十字架を背負って被災された方々の償いを一生にわたってしてもらいたいと思います。年が明けてもこの事故については追及し、監視し続けたいと思っています。
《参考》
・「今年の締めくくり10大ニュース」・・・・2010年12月31日の僕のブログ記事
2011年12月29日
【3/11を境に】
 2011年は大変な年でした。言うまでもなく、それは3月11日の東日本大震災、大津波、それに伴う福島第一原発の核惨事を意味します。あの日の前と後では日本、そして世界が一変したのではないでしょうか?少なくとも僕の中では、福島の原発事故によって1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原発事故以来、常に忘れることがなかった原発への恐怖がよみがえりました。
2011年は大変な年でした。言うまでもなく、それは3月11日の東日本大震災、大津波、それに伴う福島第一原発の核惨事を意味します。あの日の前と後では日本、そして世界が一変したのではないでしょうか?少なくとも僕の中では、福島の原発事故によって1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原発事故以来、常に忘れることがなかった原発への恐怖がよみがえりました。
そしてこのブログの記事も3月11日以降のほとんどを福島第一原発を軸とした原発に関する内容で埋め尽くしました。なぜそうしたか?それは、あれほどの事故を経験してもなお反省のかけらもない政府や東電、御用学者や原子力関係事業者や一部大手メディアなどの「原子力ムラ」と呼ばれる人たちへの言いようのない怒りと、何も変えることのできない一市民の無力感から来ています。
【先ず怒ること】
 なぜ、あれほどの事故を起こしていながら、東電の経営陣や経産省原子力安全・保安院や原子力関係の人間たちは犯罪者として裁かれないのか?なぜ、あれほどの事故を経験し、とてつもない放射性物質が大地や空気や水を汚染しても、子供たちなどを真の意味で救うべく迅速な対応が取られないのか?
なぜ、あれほどの事故を起こしていながら、東電の経営陣や経産省原子力安全・保安院や原子力関係の人間たちは犯罪者として裁かれないのか?なぜ、あれほどの事故を経験し、とてつもない放射性物質が大地や空気や水を汚染しても、子供たちなどを真の意味で救うべく迅速な対応が取られないのか?
政府の事故調査委員会の中間報告が発表されてから、NHKや民放でいろいろな福島原発事故の経過を巡るドキュメントが放送されていますが、それらを見るたびに事故当時のことを思い起こし、未だに無責任な発言を繰り返す役人や政治家、学者や東電の経営陣などを見ていると、再び心の底から怒りがこみ上げてきます。
先日、野田首相は福島原発事故の収束宣言をしましたがとんでもないことです。事故は収束するどころか、役所の縦割り主義と無責任体制のもと、さまざまな放射性物質の規制値がまたしても場当たり的に決められ、福島周辺だけでなくこれから日本全国に、もっと広範囲に深く、長く放射能汚染が広がっていかざるを得ない状況になりつつあります。
原発に無関心だった方には是非、原発とこれからどう向き合っていくか真剣に考えてほしいと思います。特に福島から遠く離れていると思っている福岡や九州のひとたちはなおさらです。原発事故は距離を選びませんし、同じような事故は九州の原発でも起きます。
ひとりの市民として、本当にひとりひとりが真剣に怒り、原子力ムラの無法と無責任と戦っていかなければ、僕たちの大地も水も空気も、そして大事な子供たちや家族も命の危険にさらされ続けていくことになるでしょう。それほど深刻な問題だということを肝に銘じておかなければなりません。ひとりでも多くそれを知ってもらうためにも来年も僕はブログで原発について書き続けようと思っています。
 2011年は大変な年でした。言うまでもなく、それは3月11日の東日本大震災、大津波、それに伴う福島第一原発の核惨事を意味します。あの日の前と後では日本、そして世界が一変したのではないでしょうか?少なくとも僕の中では、福島の原発事故によって1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原発事故以来、常に忘れることがなかった原発への恐怖がよみがえりました。
2011年は大変な年でした。言うまでもなく、それは3月11日の東日本大震災、大津波、それに伴う福島第一原発の核惨事を意味します。あの日の前と後では日本、そして世界が一変したのではないでしょうか?少なくとも僕の中では、福島の原発事故によって1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原発事故以来、常に忘れることがなかった原発への恐怖がよみがえりました。そしてこのブログの記事も3月11日以降のほとんどを福島第一原発を軸とした原発に関する内容で埋め尽くしました。なぜそうしたか?それは、あれほどの事故を経験してもなお反省のかけらもない政府や東電、御用学者や原子力関係事業者や一部大手メディアなどの「原子力ムラ」と呼ばれる人たちへの言いようのない怒りと、何も変えることのできない一市民の無力感から来ています。
【先ず怒ること】
 なぜ、あれほどの事故を起こしていながら、東電の経営陣や経産省原子力安全・保安院や原子力関係の人間たちは犯罪者として裁かれないのか?なぜ、あれほどの事故を経験し、とてつもない放射性物質が大地や空気や水を汚染しても、子供たちなどを真の意味で救うべく迅速な対応が取られないのか?
なぜ、あれほどの事故を起こしていながら、東電の経営陣や経産省原子力安全・保安院や原子力関係の人間たちは犯罪者として裁かれないのか?なぜ、あれほどの事故を経験し、とてつもない放射性物質が大地や空気や水を汚染しても、子供たちなどを真の意味で救うべく迅速な対応が取られないのか?政府の事故調査委員会の中間報告が発表されてから、NHKや民放でいろいろな福島原発事故の経過を巡るドキュメントが放送されていますが、それらを見るたびに事故当時のことを思い起こし、未だに無責任な発言を繰り返す役人や政治家、学者や東電の経営陣などを見ていると、再び心の底から怒りがこみ上げてきます。
先日、野田首相は福島原発事故の収束宣言をしましたがとんでもないことです。事故は収束するどころか、役所の縦割り主義と無責任体制のもと、さまざまな放射性物質の規制値がまたしても場当たり的に決められ、福島周辺だけでなくこれから日本全国に、もっと広範囲に深く、長く放射能汚染が広がっていかざるを得ない状況になりつつあります。
原発に無関心だった方には是非、原発とこれからどう向き合っていくか真剣に考えてほしいと思います。特に福島から遠く離れていると思っている福岡や九州のひとたちはなおさらです。原発事故は距離を選びませんし、同じような事故は九州の原発でも起きます。
ひとりの市民として、本当にひとりひとりが真剣に怒り、原子力ムラの無法と無責任と戦っていかなければ、僕たちの大地も水も空気も、そして大事な子供たちや家族も命の危険にさらされ続けていくことになるでしょう。それほど深刻な問題だということを肝に銘じておかなければなりません。ひとりでも多くそれを知ってもらうためにも来年も僕はブログで原発について書き続けようと思っています。
2011年01月04日
【あの転倒男?】
「禍を転じて福となす」とはまさにこんな人のことを言うのではないでしょうか。
 『商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社、西宮神社(兵庫県西宮市)で、毎年1月10日に行われる「開門神事 福男選び」。99年にトップを走りながらゴール直前で転倒し、同年のクリスマスイブにはオートバイで転び右足に後遺症が残った男性がいる。その後、開門神事で献身的に活動し、神社の後援団体「開門神事講社」の初代講長に就任、裏方の雑踏警備などを担当する。「全ての人に福を持って帰ってほしい」と願っている。
『商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社、西宮神社(兵庫県西宮市)で、毎年1月10日に行われる「開門神事 福男選び」。99年にトップを走りながらゴール直前で転倒し、同年のクリスマスイブにはオートバイで転び右足に後遺症が残った男性がいる。その後、開門神事で献身的に活動し、神社の後援団体「開門神事講社」の初代講長に就任、裏方の雑踏警備などを担当する。「全ての人に福を持って帰ってほしい」と願っている。
開門神事は、門から本殿までの約230メートルを駆け抜け、上位3人はその年の福男と呼ばれる。同県尼崎市の会社員、平尾亮さん(34)は大学陸上部の現役選手だった97年と98年、2度にわたり2着の「二番福」に輝いた。
しかし、翌99年の福男選び。1列目中央の絶好の位置からスタートを切り、先頭を走ったが、ゴールの本殿前約5メートルで、足がもつれて転倒、後続に次々抜かれた。そのシーンはテレビで繰り返し放送され、「日本一不幸な男」と呼ばれた。この年のクリスマスイブには、オートバイで名神高速を走行中に転倒、大型トラックにひかれ大けがをした。
入院生活で、ふさぎ込みがちだった平尾さんを前向きに変えたのが、大学の同級生の言葉だった。「えべっさんが、命を守ってくれたんじゃないか」
次第に感謝の気持ちが湧き、01年には一時退院して松葉づえで福男選びに参加した。
8年前からは開門神事の度に整理券を配ったり、交通整理をしたりするなどボランティアをした。神社側が福男選びの元参加者に呼び掛け、09年に設立した開門神事講社の初代講長に就任。本番では危険なゲタ履きで走る人がいないかなど、服装指導も担当する。
今年の開門神事でも、平尾さんは松葉づえをつきながら安全を守る。「もし(1着の)一番福になっていたら、その後は開門神事に関わっていなかった。本殿前での転倒も、交通事故も不幸ではなく、えべっさんと自分とを結びつけてくれた一つの出来事だったと思っている」と語った。』(1月3日付毎日新聞)
【今でも鮮明に記憶】
 この開門神事での転倒事件、僕も今でもはっきりとテレビの映像を覚えています。この記事で99年にあったと書いてあるのでもう10年ちかく前のことだったんですね。それほど時間が経ったとは思っていませんでしたが、あの時必死で本殿に向かって走っていく無数の若者たちの中で、ゴール寸前に転倒して涙を呑んだ平尾さんの姿は何度も何度もテレビのニュースで放映されました。「なんとドジなんだろう。」と僕もそのときには思ったものでした。
この開門神事での転倒事件、僕も今でもはっきりとテレビの映像を覚えています。この記事で99年にあったと書いてあるのでもう10年ちかく前のことだったんですね。それほど時間が経ったとは思っていませんでしたが、あの時必死で本殿に向かって走っていく無数の若者たちの中で、ゴール寸前に転倒して涙を呑んだ平尾さんの姿は何度も何度もテレビのニュースで放映されました。「なんとドジなんだろう。」と僕もそのときには思ったものでした。
その平尾さんが、同じ年のクリスマスにもバイクで転倒して怪我をしたことや、その後一時落ち込んだものの、「えべっさんが命を守ってくれた」との思いから気を取り直し、それからは開門神事に参加者の事故防止のために自己奉仕に取り組んでいたとは本当に素晴らしい話ですよね。
人間いつどんなときに、どんなことが起こるかわかりません。今を精いっぱい生きることと、どんな不幸なことが自分に降りかかっても決してあきらめないで、逆にそれをバネにして常にプラス志向で生きることの大切さを平尾さんは身をもって教えてくれました。
ありがとう、平尾さん。2011年の最初に記事としてふさわしいと思いブログに取り上げさせていただきました。さあ、新しい年を迎えて僕らもみなさんも平尾さんに負けないように頑張っていきましょう。
「禍を転じて福となす」とはまさにこんな人のことを言うのではないでしょうか。
 『商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社、西宮神社(兵庫県西宮市)で、毎年1月10日に行われる「開門神事 福男選び」。99年にトップを走りながらゴール直前で転倒し、同年のクリスマスイブにはオートバイで転び右足に後遺症が残った男性がいる。その後、開門神事で献身的に活動し、神社の後援団体「開門神事講社」の初代講長に就任、裏方の雑踏警備などを担当する。「全ての人に福を持って帰ってほしい」と願っている。
『商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社、西宮神社(兵庫県西宮市)で、毎年1月10日に行われる「開門神事 福男選び」。99年にトップを走りながらゴール直前で転倒し、同年のクリスマスイブにはオートバイで転び右足に後遺症が残った男性がいる。その後、開門神事で献身的に活動し、神社の後援団体「開門神事講社」の初代講長に就任、裏方の雑踏警備などを担当する。「全ての人に福を持って帰ってほしい」と願っている。開門神事は、門から本殿までの約230メートルを駆け抜け、上位3人はその年の福男と呼ばれる。同県尼崎市の会社員、平尾亮さん(34)は大学陸上部の現役選手だった97年と98年、2度にわたり2着の「二番福」に輝いた。
しかし、翌99年の福男選び。1列目中央の絶好の位置からスタートを切り、先頭を走ったが、ゴールの本殿前約5メートルで、足がもつれて転倒、後続に次々抜かれた。そのシーンはテレビで繰り返し放送され、「日本一不幸な男」と呼ばれた。この年のクリスマスイブには、オートバイで名神高速を走行中に転倒、大型トラックにひかれ大けがをした。
入院生活で、ふさぎ込みがちだった平尾さんを前向きに変えたのが、大学の同級生の言葉だった。「えべっさんが、命を守ってくれたんじゃないか」
次第に感謝の気持ちが湧き、01年には一時退院して松葉づえで福男選びに参加した。
8年前からは開門神事の度に整理券を配ったり、交通整理をしたりするなどボランティアをした。神社側が福男選びの元参加者に呼び掛け、09年に設立した開門神事講社の初代講長に就任。本番では危険なゲタ履きで走る人がいないかなど、服装指導も担当する。
今年の開門神事でも、平尾さんは松葉づえをつきながら安全を守る。「もし(1着の)一番福になっていたら、その後は開門神事に関わっていなかった。本殿前での転倒も、交通事故も不幸ではなく、えべっさんと自分とを結びつけてくれた一つの出来事だったと思っている」と語った。』(1月3日付毎日新聞)
【今でも鮮明に記憶】
 この開門神事での転倒事件、僕も今でもはっきりとテレビの映像を覚えています。この記事で99年にあったと書いてあるのでもう10年ちかく前のことだったんですね。それほど時間が経ったとは思っていませんでしたが、あの時必死で本殿に向かって走っていく無数の若者たちの中で、ゴール寸前に転倒して涙を呑んだ平尾さんの姿は何度も何度もテレビのニュースで放映されました。「なんとドジなんだろう。」と僕もそのときには思ったものでした。
この開門神事での転倒事件、僕も今でもはっきりとテレビの映像を覚えています。この記事で99年にあったと書いてあるのでもう10年ちかく前のことだったんですね。それほど時間が経ったとは思っていませんでしたが、あの時必死で本殿に向かって走っていく無数の若者たちの中で、ゴール寸前に転倒して涙を呑んだ平尾さんの姿は何度も何度もテレビのニュースで放映されました。「なんとドジなんだろう。」と僕もそのときには思ったものでした。その平尾さんが、同じ年のクリスマスにもバイクで転倒して怪我をしたことや、その後一時落ち込んだものの、「えべっさんが命を守ってくれた」との思いから気を取り直し、それからは開門神事に参加者の事故防止のために自己奉仕に取り組んでいたとは本当に素晴らしい話ですよね。
人間いつどんなときに、どんなことが起こるかわかりません。今を精いっぱい生きることと、どんな不幸なことが自分に降りかかっても決してあきらめないで、逆にそれをバネにして常にプラス志向で生きることの大切さを平尾さんは身をもって教えてくれました。
ありがとう、平尾さん。2011年の最初に記事としてふさわしいと思いブログに取り上げさせていただきました。さあ、新しい年を迎えて僕らもみなさんも平尾さんに負けないように頑張っていきましょう。
2010年12月03日
【不思議な縁】
 月曜日の夜、縁あってか13年ぶりにお会いした大先生が中洲のライブハウス「トロンボーン」でジャズボーカルを披露されるということで万難を排して出かけて、その素晴らしい歌声と大人の魅力に感激し、しばし時の流れを忘れるほどでした。
月曜日の夜、縁あってか13年ぶりにお会いした大先生が中洲のライブハウス「トロンボーン」でジャズボーカルを披露されるということで万難を排して出かけて、その素晴らしい歌声と大人の魅力に感激し、しばし時の流れを忘れるほどでした。
その大先生とは、もうかれこれ15~16年ほど前に通訳ガイド試験に合格し、晴れてガイドとしての最初の講習を受けに大阪に行った時に講師をされていた方で、お名前をランデル洋子さんと言います。また博多でお会いできるなんて思いもしませんでした。
【通訳界の著名人がジャズ界に】
ランデル洋子さんと言えば、通訳ガイドや通訳の業界の方なら一度は聞いたことがあるお名前ではないでしょうか。名古屋出身で南山大学卒業後、通訳としてロッド・スチュアート等の有名外人アーティストにアテンドしたり、24もの英語を使う仕事を経験、その実力を買われてラジオやテレビにもたびたび出演、2005年よりNPO法人GICSS(ジックス)通訳ガイド&コミュニケーション・スキル研究会(http://www.gicss.org/)を主宰。全国約500名の通訳案内士国家資格保持者のメンバーに対して、ガイド業務研修や日本文化紹介のスキル研修指導、異文化間コミュニケーション・スキル研修などを行い、会員相互の交流チャンスを提供したり、企業研修の講師や講演で、全国をまわっておられます。
 そして、今回福岡で初披露されたジャズボーカル。最初は趣味で始めたそうですが、その多彩な才能が音楽にも当然生かされついにプロの歌手としてデビューしたのです。本人いわく、「遅咲き満開」ではありますが、誰もが認める大人の魅力満載の本格派です。
そして、今回福岡で初披露されたジャズボーカル。最初は趣味で始めたそうですが、その多彩な才能が音楽にも当然生かされついにプロの歌手としてデビューしたのです。本人いわく、「遅咲き満開」ではありますが、誰もが認める大人の魅力満載の本格派です。
実は今回、九州通訳ガイド協会というガイド協会の団体の招きで数年ぶりに福岡に来られたのですが、異文化コミュニケーションの研修の講師だけでなく、歌を通したコミュニケーションも披露されて九州のガイド通訳の方々を中心に大きな感動を与えてくれました。
これからもますます歌に仕事に磨きをかけて、また福岡、いや博多の地においでいただけるように心から祈っております。ランデル先生、どうもありがとうございました。
 月曜日の夜、縁あってか13年ぶりにお会いした大先生が中洲のライブハウス「トロンボーン」でジャズボーカルを披露されるということで万難を排して出かけて、その素晴らしい歌声と大人の魅力に感激し、しばし時の流れを忘れるほどでした。
月曜日の夜、縁あってか13年ぶりにお会いした大先生が中洲のライブハウス「トロンボーン」でジャズボーカルを披露されるということで万難を排して出かけて、その素晴らしい歌声と大人の魅力に感激し、しばし時の流れを忘れるほどでした。その大先生とは、もうかれこれ15~16年ほど前に通訳ガイド試験に合格し、晴れてガイドとしての最初の講習を受けに大阪に行った時に講師をされていた方で、お名前をランデル洋子さんと言います。また博多でお会いできるなんて思いもしませんでした。
【通訳界の著名人がジャズ界に】
ランデル洋子さんと言えば、通訳ガイドや通訳の業界の方なら一度は聞いたことがあるお名前ではないでしょうか。名古屋出身で南山大学卒業後、通訳としてロッド・スチュアート等の有名外人アーティストにアテンドしたり、24もの英語を使う仕事を経験、その実力を買われてラジオやテレビにもたびたび出演、2005年よりNPO法人GICSS(ジックス)通訳ガイド&コミュニケーション・スキル研究会(http://www.gicss.org/)を主宰。全国約500名の通訳案内士国家資格保持者のメンバーに対して、ガイド業務研修や日本文化紹介のスキル研修指導、異文化間コミュニケーション・スキル研修などを行い、会員相互の交流チャンスを提供したり、企業研修の講師や講演で、全国をまわっておられます。
 そして、今回福岡で初披露されたジャズボーカル。最初は趣味で始めたそうですが、その多彩な才能が音楽にも当然生かされついにプロの歌手としてデビューしたのです。本人いわく、「遅咲き満開」ではありますが、誰もが認める大人の魅力満載の本格派です。
そして、今回福岡で初披露されたジャズボーカル。最初は趣味で始めたそうですが、その多彩な才能が音楽にも当然生かされついにプロの歌手としてデビューしたのです。本人いわく、「遅咲き満開」ではありますが、誰もが認める大人の魅力満載の本格派です。実は今回、九州通訳ガイド協会というガイド協会の団体の招きで数年ぶりに福岡に来られたのですが、異文化コミュニケーションの研修の講師だけでなく、歌を通したコミュニケーションも披露されて九州のガイド通訳の方々を中心に大きな感動を与えてくれました。
これからもますます歌に仕事に磨きをかけて、また福岡、いや博多の地においでいただけるように心から祈っております。ランデル先生、どうもありがとうございました。
2010年09月08日
【収入と幸せ】
心の中ではそう思っている方が多いのではないでしょうか。
 『収入が上がるにつれ生活の満足度は上がるものの、必ずしも幸福感が増すとは限らないとする調査結果をダニエル・カーネマン米プリンストン大教授らがまとめ、米科学アカデミー紀要で7日発表する。
『収入が上がるにつれ生活の満足度は上がるものの、必ずしも幸福感が増すとは限らないとする調査結果をダニエル・カーネマン米プリンストン大教授らがまとめ、米科学アカデミー紀要で7日発表する。
「幸福は金で買えない」という通説を裏づける報告と言えそうだ。カーネマン教授は、米国人45万人以上を対象に調査会社が実施した電話調査のデータを基に、年収と幸福の関係を統計的に分析した。暮らしに対する満足度を10段階で自己評価してもらう「生活評価」の数値は、年収が増えるにつれ一貫して上昇した。
しかし、「昨日笑ったか」などの質問で測る「感情的幸福」の度合いは、年収7万5000ドル(約630万円)前後で頭打ちになっていた。
教授は「高収入で満足は得られるが、幸せになれるとは限らない」と結論している。』 (9月7日付読売新聞)
【幸せの物差し】
僕もサラリーマン生活を長く続けていて、上司や同僚、知人などを見ていてつくづくそう思います。もちろん、それなりの生活をしていくためにはある程度の収入は必要かもしれませんが、必ずしもその収入の過多が幸せに結びつかない例は枚挙にいとまがないほどたくさんあるのではないでしょうか。
仕事の満足度、妻や子供との安定した暮らし、友人や知人、会社の上司や部下との関係、自分の人生を豊かにする要素というのはいろいろあります。最低限の暮らしが出来る収入があって、自分の人生の目標や家族との良好な関係があれば、収入だけが幸せのバロメーターではないのは明らかです。
その幸せの物差しを持って、幸せかどうかを測るのはまさに自分自身です。本当の幸せをつかむためには、自分や家族の幸せを妨げようとする様々な障害に打ち勝っていくことが必要です。あなたは今、ほんとうに幸せですか?
心の中ではそう思っている方が多いのではないでしょうか。
 『収入が上がるにつれ生活の満足度は上がるものの、必ずしも幸福感が増すとは限らないとする調査結果をダニエル・カーネマン米プリンストン大教授らがまとめ、米科学アカデミー紀要で7日発表する。
『収入が上がるにつれ生活の満足度は上がるものの、必ずしも幸福感が増すとは限らないとする調査結果をダニエル・カーネマン米プリンストン大教授らがまとめ、米科学アカデミー紀要で7日発表する。「幸福は金で買えない」という通説を裏づける報告と言えそうだ。カーネマン教授は、米国人45万人以上を対象に調査会社が実施した電話調査のデータを基に、年収と幸福の関係を統計的に分析した。暮らしに対する満足度を10段階で自己評価してもらう「生活評価」の数値は、年収が増えるにつれ一貫して上昇した。
しかし、「昨日笑ったか」などの質問で測る「感情的幸福」の度合いは、年収7万5000ドル(約630万円)前後で頭打ちになっていた。
教授は「高収入で満足は得られるが、幸せになれるとは限らない」と結論している。』 (9月7日付読売新聞)
【幸せの物差し】
僕もサラリーマン生活を長く続けていて、上司や同僚、知人などを見ていてつくづくそう思います。もちろん、それなりの生活をしていくためにはある程度の収入は必要かもしれませんが、必ずしもその収入の過多が幸せに結びつかない例は枚挙にいとまがないほどたくさんあるのではないでしょうか。
仕事の満足度、妻や子供との安定した暮らし、友人や知人、会社の上司や部下との関係、自分の人生を豊かにする要素というのはいろいろあります。最低限の暮らしが出来る収入があって、自分の人生の目標や家族との良好な関係があれば、収入だけが幸せのバロメーターではないのは明らかです。
その幸せの物差しを持って、幸せかどうかを測るのはまさに自分自身です。本当の幸せをつかむためには、自分や家族の幸せを妨げようとする様々な障害に打ち勝っていくことが必要です。あなたは今、ほんとうに幸せですか?
2010年08月11日
【嘉麻市との出会い】
みなさんは「嘉麻市」という地名をご存知ですか?
 僕は福岡に居ながら恥ずかしながらつい数日前までその町の場所も地名も、町の生い立ちも全く知りませんでした。その町は福岡県のど真ん中から少し北寄りに位置する筑豊南部の人口4万人あまりの町です。
僕は福岡に居ながら恥ずかしながらつい数日前までその町の場所も地名も、町の生い立ちも全く知りませんでした。その町は福岡県のど真ん中から少し北寄りに位置する筑豊南部の人口4万人あまりの町です。
その町と僕はある展覧会がきっかけで先週末出会いました。その展覧会とは「英國Grandfather's Letters展」。仕掛け人は松任谷愛介氏。苗字に聞き覚えのある方は多いかもしれません。音楽に疎い僕でもその苗字だけは知っていました。でも知っていたのはそれだけ。「出会い」とは不思議なものです。その苗字だけしか知らなかった人の魅力にひき寄せられ、福岡市から1時間近くある「その町」に「家族」とともに出かけ、そしてその町に出会ったのです。
【織田廣喜美術館】
 その町の中心に位置する田園や民家の点在する静かな佇まいの中に織田廣喜美術館という立派な展示会場はありました。図書館と平和記念館も併設されていました。その中に小さな絵手紙が壁に掛けられたり、ガラスケースに収められたりして入場者を待っていました。100年近く前の英国の退役軍人のお爺さんがインドに住む孫4人に宛てた絵手紙の数々。愛情とユーモアのこもった筆致で書かれた動物や乗り物などのイラストの数々。そこに添えられた孫の興味を掻き立てる文章。時代を超えて心に響く絵手紙の不思議なパワーがそこにはありました。
その町の中心に位置する田園や民家の点在する静かな佇まいの中に織田廣喜美術館という立派な展示会場はありました。図書館と平和記念館も併設されていました。その中に小さな絵手紙が壁に掛けられたり、ガラスケースに収められたりして入場者を待っていました。100年近く前の英国の退役軍人のお爺さんがインドに住む孫4人に宛てた絵手紙の数々。愛情とユーモアのこもった筆致で書かれた動物や乗り物などのイラストの数々。そこに添えられた孫の興味を掻き立てる文章。時代を超えて心に響く絵手紙の不思議なパワーがそこにはありました。
さらに、それらの感動を本物にしてくれたのは先ほどご紹介した松任谷氏のやわらかい語り口でした。なんと、少ない入場者ひとりひとりに語りかけるように懇切丁寧に展覧会場を案内してくれていたのです。
【展覧会の絵】
僕は美術館に行ってそこに飾ってある絵がどんなに有名なものであっても、それほど感動を覚えた経験はあまりありません。現代の美術館は、そこに展示されてある絵や彫刻などの美術品が有名であればあるほど、また、美術館自身がそうであればあるほど、純粋な感動をそこで味わうのは有名度に反比例して小さくなるのではないかと僕は思っています。なぜならそこには大勢の入場者による喧騒や商業的なPRなどが個人の静かな鑑賞の時空間を奪うからです。
そういう意味で、今回の嘉麻市、織田廣喜美術館、英國Grandfather's Letters展、そして松任谷愛介氏との出会いは僕にとって思いもかけず新鮮ですばらしいものでした。それらすべてにこれからますます興味を引き付けられる予感がしてなりません。みなさんも一度行って見られませんか?
みなさんは「嘉麻市」という地名をご存知ですか?
その町と僕はある展覧会がきっかけで先週末出会いました。その展覧会とは「英國Grandfather's Letters展」。仕掛け人は松任谷愛介氏。苗字に聞き覚えのある方は多いかもしれません。音楽に疎い僕でもその苗字だけは知っていました。でも知っていたのはそれだけ。「出会い」とは不思議なものです。その苗字だけしか知らなかった人の魅力にひき寄せられ、福岡市から1時間近くある「その町」に「家族」とともに出かけ、そしてその町に出会ったのです。
【織田廣喜美術館】
 その町の中心に位置する田園や民家の点在する静かな佇まいの中に織田廣喜美術館という立派な展示会場はありました。図書館と平和記念館も併設されていました。その中に小さな絵手紙が壁に掛けられたり、ガラスケースに収められたりして入場者を待っていました。100年近く前の英国の退役軍人のお爺さんがインドに住む孫4人に宛てた絵手紙の数々。愛情とユーモアのこもった筆致で書かれた動物や乗り物などのイラストの数々。そこに添えられた孫の興味を掻き立てる文章。時代を超えて心に響く絵手紙の不思議なパワーがそこにはありました。
その町の中心に位置する田園や民家の点在する静かな佇まいの中に織田廣喜美術館という立派な展示会場はありました。図書館と平和記念館も併設されていました。その中に小さな絵手紙が壁に掛けられたり、ガラスケースに収められたりして入場者を待っていました。100年近く前の英国の退役軍人のお爺さんがインドに住む孫4人に宛てた絵手紙の数々。愛情とユーモアのこもった筆致で書かれた動物や乗り物などのイラストの数々。そこに添えられた孫の興味を掻き立てる文章。時代を超えて心に響く絵手紙の不思議なパワーがそこにはありました。さらに、それらの感動を本物にしてくれたのは先ほどご紹介した松任谷氏のやわらかい語り口でした。なんと、少ない入場者ひとりひとりに語りかけるように懇切丁寧に展覧会場を案内してくれていたのです。
【展覧会の絵】
僕は美術館に行ってそこに飾ってある絵がどんなに有名なものであっても、それほど感動を覚えた経験はあまりありません。現代の美術館は、そこに展示されてある絵や彫刻などの美術品が有名であればあるほど、また、美術館自身がそうであればあるほど、純粋な感動をそこで味わうのは有名度に反比例して小さくなるのではないかと僕は思っています。なぜならそこには大勢の入場者による喧騒や商業的なPRなどが個人の静かな鑑賞の時空間を奪うからです。
そういう意味で、今回の嘉麻市、織田廣喜美術館、英國Grandfather's Letters展、そして松任谷愛介氏との出会いは僕にとって思いもかけず新鮮ですばらしいものでした。それらすべてにこれからますます興味を引き付けられる予感がしてなりません。みなさんも一度行って見られませんか?
2010年05月10日
【動物も左利き?】
動物たちもみんな左利きがあるんですね。
 『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。
『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。
同紙によると、研究者たちはこれまで、左利き、右利きがあるのはヒトに限定されていると考えていたが、最近ではほとんどすべての生物が左右どちらかを主に使うよう進化したことが分かったという。
魚の場合、自分の敵となる魚や動物が接近してきた場合、右利きの目をもつ魚は時計と同じ右回りに逃げ、左利きの魚は左回りに逃げる。左右差があった方が素早く反応でき、生存の確率が高まる。
また、英クイーンズ大学(北アイルランド・ベルファスト)の研究によれば、性別で違いもあることも分かった。猫の場合、雌猫は瓶などから食べ物を引き出そうとする際、右手(右前脚)を使う傾向があるのに、雄猫は左手を使おうとする。犬の場合も同様に当てはまるという。』(5月2日付ロイター通信)
【仲間が増えた】
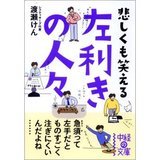 それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。
それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。
それが数十年前から、「私の彼は左利き」とかいう歌が流行ったり、外国の元首や有名人が左手でサインしていたりと、日本社会の常識が世界の常識ではないことが少しずつ浸透してきて今ではあまり左利きに対する差別はさほど強くはなくなりました。(ちなみにオバマ大統領も左手でサインしています)
そんなところに今回は動物社会でも左利きが存在し、しかもそれが生存競争にも有利に働いているというのですから、左利きの僕なんかにしてみれば嬉しい限りです。これからは異能の人が活躍する時代です。右脳人間には左利きか多いとも言います。左利きのみなさん、これからも右利き社会をどんどん変革していきましょう!!!!
動物たちもみんな左利きがあるんですね。
 『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。
『2日付の英日曜紙サンデー・タイムズは、猫、犬はもとより、オウムや魚に至るまで、ヒトと同じように手足や目に「右利き」と「左利き」があることが判明したとし、これは生存競争にも有利に働いていると報じた。同紙によると、研究者たちはこれまで、左利き、右利きがあるのはヒトに限定されていると考えていたが、最近ではほとんどすべての生物が左右どちらかを主に使うよう進化したことが分かったという。
魚の場合、自分の敵となる魚や動物が接近してきた場合、右利きの目をもつ魚は時計と同じ右回りに逃げ、左利きの魚は左回りに逃げる。左右差があった方が素早く反応でき、生存の確率が高まる。
また、英クイーンズ大学(北アイルランド・ベルファスト)の研究によれば、性別で違いもあることも分かった。猫の場合、雌猫は瓶などから食べ物を引き出そうとする際、右手(右前脚)を使う傾向があるのに、雄猫は左手を使おうとする。犬の場合も同様に当てはまるという。』(5月2日付ロイター通信)
【仲間が増えた】
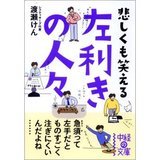 それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。
それにしてもこれは嬉しいニュースです。日本社会ではつい最近まで左利きの人たちは肩身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。僕も小さい時はすべて左利きで、両親から一部だけ右利きに修正されました。でも今でも食事のときの箸は左、絵を描くのも左です。また、字は左右両方で書くことが出来ます。すべて左だったころにイジメにあっていたのかどうか定かではありませんが、日本社会では何もかも右利きが正当ということで箸の使い方から襖の開け閉めまで右手でやるのが当たり前だったのです。それが数十年前から、「私の彼は左利き」とかいう歌が流行ったり、外国の元首や有名人が左手でサインしていたりと、日本社会の常識が世界の常識ではないことが少しずつ浸透してきて今ではあまり左利きに対する差別はさほど強くはなくなりました。(ちなみにオバマ大統領も左手でサインしています)
そんなところに今回は動物社会でも左利きが存在し、しかもそれが生存競争にも有利に働いているというのですから、左利きの僕なんかにしてみれば嬉しい限りです。これからは異能の人が活躍する時代です。右脳人間には左利きか多いとも言います。左利きのみなさん、これからも右利き社会をどんどん変革していきましょう!!!!
タグ :左利き
2009年12月31日
【今年の10大ニュース】
いよいよ今年も今日で終わり。年の最後に2009年を振り返るべく、読売新聞の読者が選んだ10大ニュースを見てみましょう。先ずは「日本編」。
1.政権交代、鳩山内閣が誕生
2.日本でも新型インフルエンザ流行
3.「裁判員制度」スタート
4.日本がWBC連覇
5.酒井法子容疑者、覚せい剤所持で逮捕
6.天皇陛下即位20年
7.高速道「上限1000円」スタート
8.イチロー選手が大リーグ史上初の9年連続200安打
9.巨人が7年ぶり21度目日本一
10.「足利事件」の菅家さん釈放 DNA鑑定に誤り
今年の日本は、昨年のリーマンショックが尾を引く中、人々の政治への不満が頂点に達し遂に政権交代に及びました。積極的に民主党を選んだと言うよりもそれしか選択肢がなかったというのが正直なところではないでしょうか。イチロー選手がWBC連覇と9年連続200安打と、二つのニュースに絡んでいるのは本当にすごいですね。
【国際編10大ニュース】
では同じく読売新聞から国際編の10大ニュースをどうぞ。
1.新型インフルエンザ大流行、世界で死者相次ぐ
2.オバマ米大統領が就任
3.マイケル・ジャクソンさん急死
4.米GM、クライスラーが相次ぎ経営破綻
5.ノーベル平和賞にオバマ大統領
6.北朝鮮が弾道ミサイル発射
7.韓国で射撃場火災、日本人客10人死亡
8.中国新疆ウイグル自治区で暴動、197人死亡
9.南太平洋、スマトラで大地震相次ぐ
10.世界陸上、ボルト選手が3冠
海外のトップニュースはオバマ大統領就任となりましたが、昨年も初の黒人大統領ということでトップでしたので2年連続です。しかも、国内はイチロー選手が関係したニュースがふたつもありましたが、海外ではオバマ大統領がノーベル平和賞でも出ており、こちらもふたつ。みんなの記憶にこれほど残ったというのはやはり偉大さの表れでしょうね。
【僕のブログの10大ニュース】
そして最後に独断と偏見で選んだ僕のブログの10大ニュースを発表します。
1.「政権交代―真価問われる民主党」・・・・・・・・・8月31日記事
2.「WBC二連覇―サムライの快挙」・・・・・・・・・3月25日記事
3.「パンデミックか―米国・メキシコのインフル」・・・4月27日記事
4.「先ずは政治的意思の表明―鳩山氏のCO2の削減目標」・9月8日記事
5.「М・ジャクソン、突然帰らぬ人に」・・・・・・・・6月29日記事
6.「閉幕まで続く緊迫―混沌のCOP15」・・・・・・12月18日記事
7.「見えてきた鳩山政権の姿勢―普天間問題」・・・・・12月16日記事
8.「転落した酒井法子がすべきこと」・・・・・・・・・8月10日記事
9.「イチローの新たなる挑戦―9年連続の200本内野安打」・9月15日記事
10.「もうノーベル賞?―オバマ大統領」・・・・・・・・10月13日記事
今年は日本人にとっては、何といっても政権交代が最も大きな出来事だったというのは僕も同感でした。政治が変わってこそ、僕の最も大きな懸念である気候変動、地球温暖化に対する取り組みも前進する可能性が見えてきます。実際、民主党になってから鳩山首相は即座にCO2削減目標を25%にすると発表しました。具体策はこれからにせよ、自民党政権と比べれば画期的な方向転換でしょう。しかし、コペンハーゲンでのCOP15は京都議定書後の世界的な地球温暖化防止に向けた枠組みが完成したとはとても言い難い状況で閉幕しました。
今年からNHKで始まった「坂の上の雲」。明治の若者の、明日を信じて国家を創っていった気概に感動させられます。僕たちは今、日本という国家の命運だけでなく、地球環境という世界の命運まで危機に瀕している時代に生きていることを深く受け止め、明治人をみならって、明治人を超える気概を持って、しかも明るく前進していかなければならないと思います。
《参考》
・「今年の締めくくり10大ニュース」・・・・2008年12月31日の僕のブログ記事
いよいよ今年も今日で終わり。年の最後に2009年を振り返るべく、読売新聞の読者が選んだ10大ニュースを見てみましょう。先ずは「日本編」。
1.政権交代、鳩山内閣が誕生
2.日本でも新型インフルエンザ流行
3.「裁判員制度」スタート
4.日本がWBC連覇
5.酒井法子容疑者、覚せい剤所持で逮捕
6.天皇陛下即位20年
7.高速道「上限1000円」スタート
8.イチロー選手が大リーグ史上初の9年連続200安打
9.巨人が7年ぶり21度目日本一
10.「足利事件」の菅家さん釈放 DNA鑑定に誤り
今年の日本は、昨年のリーマンショックが尾を引く中、人々の政治への不満が頂点に達し遂に政権交代に及びました。積極的に民主党を選んだと言うよりもそれしか選択肢がなかったというのが正直なところではないでしょうか。イチロー選手がWBC連覇と9年連続200安打と、二つのニュースに絡んでいるのは本当にすごいですね。
【国際編10大ニュース】
では同じく読売新聞から国際編の10大ニュースをどうぞ。
1.新型インフルエンザ大流行、世界で死者相次ぐ
2.オバマ米大統領が就任
3.マイケル・ジャクソンさん急死
4.米GM、クライスラーが相次ぎ経営破綻
5.ノーベル平和賞にオバマ大統領
6.北朝鮮が弾道ミサイル発射
7.韓国で射撃場火災、日本人客10人死亡
8.中国新疆ウイグル自治区で暴動、197人死亡
9.南太平洋、スマトラで大地震相次ぐ
10.世界陸上、ボルト選手が3冠
海外のトップニュースはオバマ大統領就任となりましたが、昨年も初の黒人大統領ということでトップでしたので2年連続です。しかも、国内はイチロー選手が関係したニュースがふたつもありましたが、海外ではオバマ大統領がノーベル平和賞でも出ており、こちらもふたつ。みんなの記憶にこれほど残ったというのはやはり偉大さの表れでしょうね。
【僕のブログの10大ニュース】
そして最後に独断と偏見で選んだ僕のブログの10大ニュースを発表します。
1.「政権交代―真価問われる民主党」・・・・・・・・・8月31日記事
2.「WBC二連覇―サムライの快挙」・・・・・・・・・3月25日記事
3.「パンデミックか―米国・メキシコのインフル」・・・4月27日記事
4.「先ずは政治的意思の表明―鳩山氏のCO2の削減目標」・9月8日記事
5.「М・ジャクソン、突然帰らぬ人に」・・・・・・・・6月29日記事
6.「閉幕まで続く緊迫―混沌のCOP15」・・・・・・12月18日記事
7.「見えてきた鳩山政権の姿勢―普天間問題」・・・・・12月16日記事
8.「転落した酒井法子がすべきこと」・・・・・・・・・8月10日記事
9.「イチローの新たなる挑戦―9年連続の200本内野安打」・9月15日記事
10.「もうノーベル賞?―オバマ大統領」・・・・・・・・10月13日記事
今年は日本人にとっては、何といっても政権交代が最も大きな出来事だったというのは僕も同感でした。政治が変わってこそ、僕の最も大きな懸念である気候変動、地球温暖化に対する取り組みも前進する可能性が見えてきます。実際、民主党になってから鳩山首相は即座にCO2削減目標を25%にすると発表しました。具体策はこれからにせよ、自民党政権と比べれば画期的な方向転換でしょう。しかし、コペンハーゲンでのCOP15は京都議定書後の世界的な地球温暖化防止に向けた枠組みが完成したとはとても言い難い状況で閉幕しました。
今年からNHKで始まった「坂の上の雲」。明治の若者の、明日を信じて国家を創っていった気概に感動させられます。僕たちは今、日本という国家の命運だけでなく、地球環境という世界の命運まで危機に瀕している時代に生きていることを深く受け止め、明治人をみならって、明治人を超える気概を持って、しかも明るく前進していかなければならないと思います。
《参考》
・「今年の締めくくり10大ニュース」・・・・2008年12月31日の僕のブログ記事
2009年12月30日
【不況反映?】
年末年始の過ごし方にも不況の影が忍び寄っているようです。
 『年末年始の過ごし方について、インターネット調査会社「マクロミル」(東京)が調べたところ、9割以上が「家で過ごす」と答え、約2割が初売りや旅行などの出費を「減らす」と考えていることが26日、分かった。
『年末年始の過ごし方について、インターネット調査会社「マクロミル」(東京)が調べたところ、9割以上が「家で過ごす」と答え、約2割が初売りや旅行などの出費を「減らす」と考えていることが26日、分かった。
同社は「給料が減ったとの回答も多く、長引く深刻な不況を反映した結果では」としている。
同社は今月中旬、全国の成人男女に調査を実施。1000人から有効回答を得た。
年末年始の予定は、「自宅で過ごす」が71.2%でトップ。親や義理の親が住む実家が20.3%で、計91.5%が家で過ごすと答えた。
年末年始の出費予定を聞くと、「減らす」が21.0%で「増やす」の8.8%を大きく上回った。「減らす」と答えた人に具体的な中身を複数回答で聞くと「外食や家での食費」(64.8%)が最も多く、続いて「初売りなどの買い物」(51.0%)や「旅行」(23.8%)、「お年玉」(11.0%)などが挙がった。自由回答では「ボーナスが出なかったので買い物を控える」(36歳未婚女性)などの声が寄せられた。』(12月26日付ロイター通信)
【ゆっくり静養】
この記事にあるように、今年は例年以上に自宅で過ごすと考えている人が多くなったようですが、自宅で過ごせば余計な出費はありませんし、なにより家族全員での休日をゆっくり過ごすことができますからいいことだと思います。
僕自身もこの年末年始は例年通り実家と家でゆっくり過ごします。ここ数年と比べると暦の休みの関係であまり長い休みとはなりませんが、それでも年間の中では家族と過ごせる貴重な休暇に変わりはありません。
年末年始に国内外に旅行に行けば料理を準備しないでいいぶん、奥様の負担は軽くなりますが、シーズンの特別料金の支払いで家計の負担が重くなるわけですからここは我慢してもっと安く旅行に行ける時期を選ぶべきでしょう。
家でじっくり過ぎゆく1年の反省と新しい年の目標を作るのも大切なことではないでしょうか。みなさんは年末年始、どう過ごされますか?
年末年始の過ごし方にも不況の影が忍び寄っているようです。
 『年末年始の過ごし方について、インターネット調査会社「マクロミル」(東京)が調べたところ、9割以上が「家で過ごす」と答え、約2割が初売りや旅行などの出費を「減らす」と考えていることが26日、分かった。
『年末年始の過ごし方について、インターネット調査会社「マクロミル」(東京)が調べたところ、9割以上が「家で過ごす」と答え、約2割が初売りや旅行などの出費を「減らす」と考えていることが26日、分かった。同社は「給料が減ったとの回答も多く、長引く深刻な不況を反映した結果では」としている。
同社は今月中旬、全国の成人男女に調査を実施。1000人から有効回答を得た。
年末年始の予定は、「自宅で過ごす」が71.2%でトップ。親や義理の親が住む実家が20.3%で、計91.5%が家で過ごすと答えた。
年末年始の出費予定を聞くと、「減らす」が21.0%で「増やす」の8.8%を大きく上回った。「減らす」と答えた人に具体的な中身を複数回答で聞くと「外食や家での食費」(64.8%)が最も多く、続いて「初売りなどの買い物」(51.0%)や「旅行」(23.8%)、「お年玉」(11.0%)などが挙がった。自由回答では「ボーナスが出なかったので買い物を控える」(36歳未婚女性)などの声が寄せられた。』(12月26日付ロイター通信)
【ゆっくり静養】
この記事にあるように、今年は例年以上に自宅で過ごすと考えている人が多くなったようですが、自宅で過ごせば余計な出費はありませんし、なにより家族全員での休日をゆっくり過ごすことができますからいいことだと思います。
僕自身もこの年末年始は例年通り実家と家でゆっくり過ごします。ここ数年と比べると暦の休みの関係であまり長い休みとはなりませんが、それでも年間の中では家族と過ごせる貴重な休暇に変わりはありません。
年末年始に国内外に旅行に行けば料理を準備しないでいいぶん、奥様の負担は軽くなりますが、シーズンの特別料金の支払いで家計の負担が重くなるわけですからここは我慢してもっと安く旅行に行ける時期を選ぶべきでしょう。
家でじっくり過ぎゆく1年の反省と新しい年の目標を作るのも大切なことではないでしょうか。みなさんは年末年始、どう過ごされますか?
タグ :年末年始
2009年11月11日
【「魔」が刺す?】
洗濯物の中に蜂が潜んでいたことはありませんか?
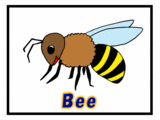 『洗濯したばかりの服を着たらチクリ--。こんな蜂の被害が、11月に集中していることが東京消防庁の調査で明らかになった。蜂は寒さをしのぐために巣ごもりする習性があり、洗濯物や布団に潜むことがある。冬に向かう季節を中心にけが人が相次ぎ、11月は1年の約4分の1を占める。同庁は「洗濯物や布団を取り込む際はよくはたき、蜂が付いていないか注意してほしい」と呼び掛けている。
『洗濯したばかりの服を着たらチクリ--。こんな蜂の被害が、11月に集中していることが東京消防庁の調査で明らかになった。蜂は寒さをしのぐために巣ごもりする習性があり、洗濯物や布団に潜むことがある。冬に向かう季節を中心にけが人が相次ぎ、11月は1年の約4分の1を占める。同庁は「洗濯物や布団を取り込む際はよくはたき、蜂が付いていないか注意してほしい」と呼び掛けている。
東京消防庁によると、06~08年に東京都内で蜂に刺され救急車で病院に運ばれた人は計965人。主に山の散策などアウトドア活動中の被害が中心で、月別では8月の213人が最も多く、続いて9月181人、7月162人と夏場が大部分を占めている。
10月以降、被害は下火になるものの、数十件に上る月もあり、同消防庁内で「夏が終わっても救急搬送が多いのはなぜなのか」と疑問の声が上がった。このため、多摩動物公園に問い合わせたところアシナガバチなどは寒くなると巣ごもりする習性があり、洗濯物や布団に隠れることが分かったという。
そこで、08年までの3年間の被害例を初めて詳細に調べたところ、「干したズボンやシャツを着たら刺された」「布団に潜んでいた蜂に刺された」というケースが148件あり、月別では11月が38人と最多で12月28件、10月21件と続いた。』(11月7日付毎日新聞)
【家に侵入する生き物】
最近世界各地で大量の蜂が忽然と消えてしまうという現象が話題になっていますが、そういえば自宅の庭に咲くツツジなどの花の蜜を吸いに来ていた蜂の姿がめっきり少なくなったような気がします。気候変動の影響なのか、原因は特定できていないようですが、気候の変化だけでなく都市化の影響などで家の周りにいる生物たちも数十年前とは比べものにならないくらい変化しているのではないでしょうか。
僕の家には昔はムカデやハエやゴキブリはよくいましたが、今はほとんど見かけません。また道路にまでよく出没していたアオダイショウなどの蛇も全く見かけることがなくなりました。小川のメダカもいなくなったし、そういえばアマガエルもほとんど見かけなくなりました。僕の家に限って言えば、未だに多いのはヤモリ君でしょうか。
冒頭紹介しました洗濯物に混じって進入する蜂だけでなく、昆虫や爬虫類が家に入ってくるのはあまり気持ちのいいものではないですが、生き物たちの姿が極端に減っているのは自然環境のとてつもない変化を彼らが身をもって人間に教えてくれているのかもしれません。
洗濯物の中に蜂が潜んでいたことはありませんか?
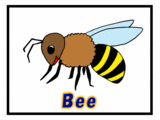 『洗濯したばかりの服を着たらチクリ--。こんな蜂の被害が、11月に集中していることが東京消防庁の調査で明らかになった。蜂は寒さをしのぐために巣ごもりする習性があり、洗濯物や布団に潜むことがある。冬に向かう季節を中心にけが人が相次ぎ、11月は1年の約4分の1を占める。同庁は「洗濯物や布団を取り込む際はよくはたき、蜂が付いていないか注意してほしい」と呼び掛けている。
『洗濯したばかりの服を着たらチクリ--。こんな蜂の被害が、11月に集中していることが東京消防庁の調査で明らかになった。蜂は寒さをしのぐために巣ごもりする習性があり、洗濯物や布団に潜むことがある。冬に向かう季節を中心にけが人が相次ぎ、11月は1年の約4分の1を占める。同庁は「洗濯物や布団を取り込む際はよくはたき、蜂が付いていないか注意してほしい」と呼び掛けている。東京消防庁によると、06~08年に東京都内で蜂に刺され救急車で病院に運ばれた人は計965人。主に山の散策などアウトドア活動中の被害が中心で、月別では8月の213人が最も多く、続いて9月181人、7月162人と夏場が大部分を占めている。
10月以降、被害は下火になるものの、数十件に上る月もあり、同消防庁内で「夏が終わっても救急搬送が多いのはなぜなのか」と疑問の声が上がった。このため、多摩動物公園に問い合わせたところアシナガバチなどは寒くなると巣ごもりする習性があり、洗濯物や布団に隠れることが分かったという。
そこで、08年までの3年間の被害例を初めて詳細に調べたところ、「干したズボンやシャツを着たら刺された」「布団に潜んでいた蜂に刺された」というケースが148件あり、月別では11月が38人と最多で12月28件、10月21件と続いた。』(11月7日付毎日新聞)
【家に侵入する生き物】
最近世界各地で大量の蜂が忽然と消えてしまうという現象が話題になっていますが、そういえば自宅の庭に咲くツツジなどの花の蜜を吸いに来ていた蜂の姿がめっきり少なくなったような気がします。気候変動の影響なのか、原因は特定できていないようですが、気候の変化だけでなく都市化の影響などで家の周りにいる生物たちも数十年前とは比べものにならないくらい変化しているのではないでしょうか。
僕の家には昔はムカデやハエやゴキブリはよくいましたが、今はほとんど見かけません。また道路にまでよく出没していたアオダイショウなどの蛇も全く見かけることがなくなりました。小川のメダカもいなくなったし、そういえばアマガエルもほとんど見かけなくなりました。僕の家に限って言えば、未だに多いのはヤモリ君でしょうか。
冒頭紹介しました洗濯物に混じって進入する蜂だけでなく、昆虫や爬虫類が家に入ってくるのはあまり気持ちのいいものではないですが、生き物たちの姿が極端に減っているのは自然環境のとてつもない変化を彼らが身をもって人間に教えてくれているのかもしれません。







