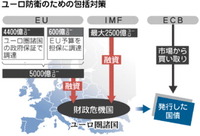2008年05月20日
小さな変化ではあるけれど、米国人の意識が変わり始めていることを予感させる記事が目に留まりました。
5月5日号のタイム誌の環境トピック(Going Green)に、 「庭をどう育んでいくか?」("How Does the Garden Grow?")と題して庭が緑に包まれていても必ずしも環境にやさしいわけではないという問題提起をしています。
いったい、どういうことなんでしょうか?
【物量作戦からの脱却】
 アメリカ人の中流家庭では庭にスプリンクラーを設置して、決まった時間に水を大量に散布するのは常識です。驚くべきことに生活用水の50%以上が庭の水撒きに使われているのです。
アメリカ人の中流家庭では庭にスプリンクラーを設置して、決まった時間に水を大量に散布するのは常識です。驚くべきことに生活用水の50%以上が庭の水撒きに使われているのです。さすがの浪費好きのアメリカ人も、最近の地球温暖化の報道などを知ってこういうことではダメだと思ってきたのでしょう。ゼリスケーピング("xeriscaping")という水や化学肥料を極力使わない庭造りが最近流行っているとのこと。(ちなみにxeriとはギリシア語でdryを意味するxerosから来ています)
その手法の例を写真の番号順にご紹介しましょう。
1.先ずは芝生エリアの制限(ration your turf)。水を大量に使う芝生は必要最小限に。
2.次はマルチング(Mulching)。植物の周りに石や木屑を置いて水分の蒸発を防ぎます。
3.ドリップ・エミッター(drip emitter)の活用。霧状の水を放出する器具のこと。日本ではあるのでしょうか?
4.堆肥の活用。
【先人の知恵】
アメリカにいたときに、砂漠であれ、都会であれ、大量の水を散布することで成り立っている庭を見たときに、「こんなやり方はいつまでも続かないだろう」と思っていました。日本もアメリカ礼賛が長く続きましたから、同じようなものかも知れません。最近、中国の郊外でもアメリカ的なマンションが林立し、スプリンクラーのある庭が成功のシンボルのようになっているそうですが、気候変動や資源枯渇が現実に人類の未来を脅かし始めた現在、人々の価値観も大きな軌道修正が求められています。大量浪費社会のアメリカで一般市民に少しでもその兆しが出てきたのであればうれしい限りです。
それにして、このゼリスケーピング("xeriscaping")という新語、タイム誌はdry landscapingと解説していますが、これって日本では水のない庭園「枯山水」としてはるか昔の平安時代にその様式が確立されています。
環境にやさしくといった意識ではなかったにしても、水利のよくない都市地域で発達した枯山水の精神は少ない資源を大切に使う日本の先人達の偉大なる知恵を感じさせます。日本はまだまだ世界に貢献できる素晴らしい価値観を沢山持っているのです。 みなさんはどう思われますか?
ゼリスケーピング・・・始めて知りました!!
勉強になりました^^有難うゴザイマス。
さて・・・我が家の庭には小さいながらも「枯山水」(もどき)
があるのですよ(笑)この庭、結構昔に作られたもの
らしく、家を建て替えるときにも残しておきました。日本には
もう同じような庭を造れる庭師さんはいないと母が言って
いたような・・・。本当かどうかはわかりませんが、昨今の
マンション流行りで庭師さんの技術も変わって来ているの
かもしれませんね。だとしたらちょっと残念!
Posted by めありー at 2008年05月20日 22:23
めありーさん、僕も知りませんでした。ときどき、タイムってためになりますね。庭師さんも伝統的な庭を作れる人はどんどん減ってきているんでしょうね。残念です。
Posted by luckymentai at 2008年05月21日 04:41
at 2008年05月21日 04:41
xeriscapingについては初耳です。
私のブログでもリンクをはらせていただきました。
ちなみに我が家も猫の額よりは大きな庭がありますが、大家さんが頼んでいる庭師さんはテキトーなので1ヶ月に1回もやってこないのです。本当にいいかげんです。
なので、ほぼ10日に1回は芝刈りをしています。芝以外のところは木屑でマルチングして、保湿+雑草が生えないようにしています。
Posted by snow_islan_ca at 2008年05月24日 04:52
この記事は記事自体は短いのですが、米国人の意識の変化が現れていると思い取り上げました。米国の大量消費社会の象徴のようなスプリンクラーと芝生。今は中国の上海の郊外とかにどんどん建設が進む高級住宅の庭にそのお株を取られてるみたいです。恐ろしいことです。
Posted by luckymentai at 2008年05月24日 05:15